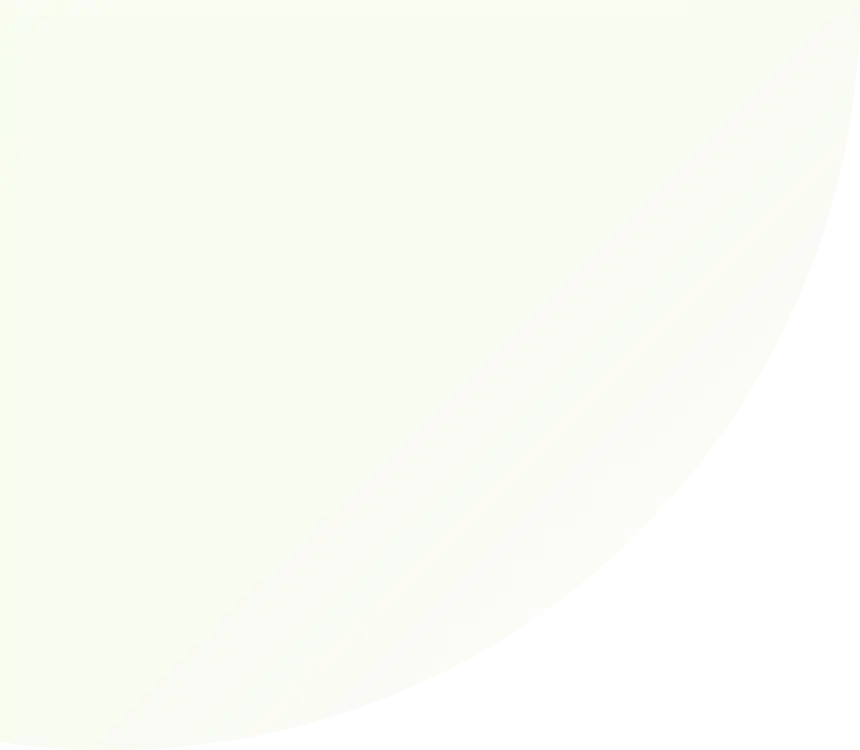
保温のためではなく、直射日光を遮ることを目的にしています。葉に日光が当たることでアミノ酸のテアニンがカテキンに変化します。日光を遮ることでその成分変化を抑えます。渋み成分であるカテキンの増加を減らし、旨味成分であるテアニンを残す栽培技術で室町時代の後期からの伝統製法(覆い下栽培)です。
新茶の季節は遅霜が降りやすく、地表付近は一時的に氷点下になります。その時に葉の中の水分が凍ることで、新芽が枯れる場合があります。そのため上空の暖かい空気層を地表に扇風機で送ることで霜が降りないようにするためです。
コンビニやスーパー、通信販売など様々に宇治茶を購入することは出来ますが、おすすめは宇治茶専門店でお買い求めいただくことです。さらには試飲して好みのお茶を見つけていただくとともに、店員さんに淹れ方を聞いたいただくことをおすすめします。(試飲可能かは店舗にご相談ください)
茶生産者が作ったお茶を購入したお茶は「荒茶」という形態で、「荒茶」の中には、「本茶」と呼ばれる葉の部分と「出物」と呼ばれる茎や粉や葉の固くなったものがあります。「荒茶」からそれぞれに選り分ける作業や、「合組」という異なる本茶と本茶を配合ブレンドし、お客様の好みに合わせたお茶に仕上げています。そして各地の得意先に発送しています。
明治時代まで京都府南部に巨椋池(現在は干拓地)があり、その池の周辺の地域であった宇治に茶づくりが鎌倉時代に伝わります。製茶技術の進歩により京都府南部や京都府の北部エリアまで広がり、さらには近隣の他府県エリアまで製茶が広がっています。それらのお茶を仕入れて加工する茶問屋が京都府内に展開していています。
お茶壺道中は、宇治から江戸の将軍家たちまで茶壺に詰められたお茶を運ぶ大名行列さながらの行事で江戸の初めから幕末まで続きました。茶壺の中身は、お抹茶の原料の碾茶(てんちゃ)が入っていいて、江戸に着いてから抹茶に挽かれていました。
平成の初めより、食品の法制度が進む中、平成16年に全国組織である日本茶業中央会が定めた「緑茶の表示基準」にともない、日本茶業中央会の会員団体である京都府茶業会議所は、宇治茶の定義を同年に決定して、それに基づいて宇治茶を取り扱っています。宇治茶の定義「宇治茶は、歴史・文化・地理・気象等総合的な見地に鑑み、宇治茶としてともに発展してきた当該産地である京都・奈良・滋賀・三重の四府県産茶で、京都府内業者が府内で仕上げ加工したものである。」
京都府内の茶生産者の団体と茶流通加工業者の団体が、会員で京都府内の茶業を明治時代から宇治茶の品質を保ち、普及に努めてきました。最近では、宇治茶の文化保存と振興を事業の中心に活動しています。
その年に初めて取れた食材を食べると長生きすると考えられ、「初物」と呼ばれて重宝されました。八十八夜は、新茶の季節として、昔から「初物」のひとつとして、全国で飲まれてました。この頃とれた新茶(特に煎茶)は、香りが豊かで旨味がたくさん含まれています。
お茶の成分には、カフェインの成分があります。その影響があるかもしれません。ただし、お茶を飲んだ人全員が、眠れなくなるかと言えば、そうではないようで、体調にもよりますし、個人差はあるようです。