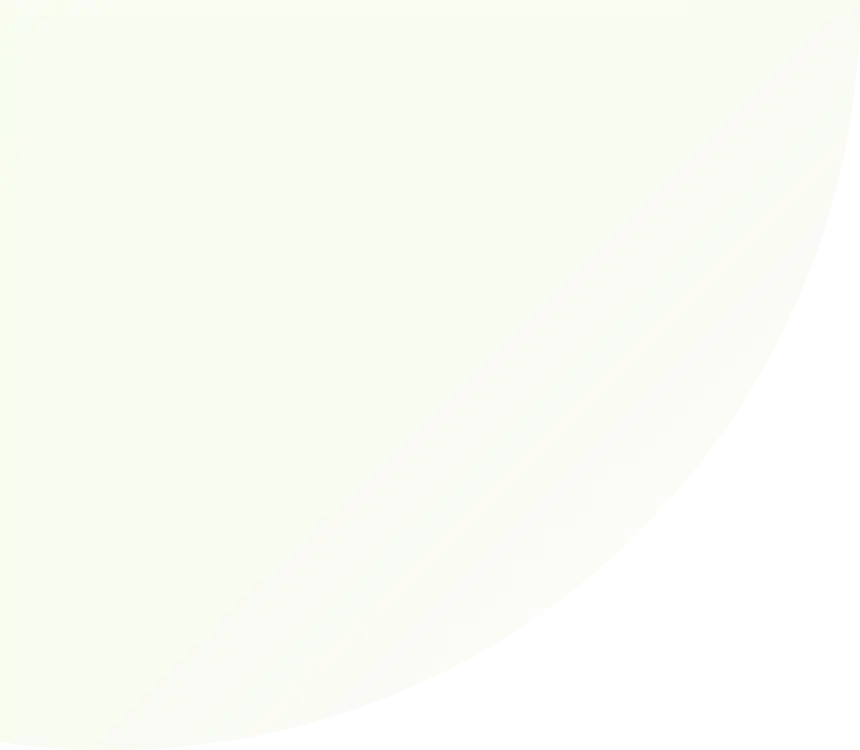

京都における碾茶生産の歩み・前編

堀井 長太郎

800年前に栄西禅師が中国より持ち帰った茶の実が時代を経て、室町時代には抹茶の誕生を迎える。日本独自の覆い下栽培を確立し、茶の芽を蒸した後に乾燥し、その葉を石臼で挽く抹茶は日本・宇治で誕生した独自の飲み物である。抹茶は豊臣時代に隆盛を迎え、日本文化の象徴である「茶道」が確立されたことも抹茶にとっても大きな意味があった。茶を所有することが権力者の象徴であったことは、足利将軍から徳川時代まで続き、より一層抹茶の飲料としての特殊性を見ることが出来る。茶師という制度で宇治の抹茶は保護され、さらに覆い下栽培は宇治以外ではその栽培方法が許されることなく、如何に宇治茶の地位の高さを物語っている事がよくわかる。
その原料となる碾茶の生産製法を振り返ってみよう。宇治上林記念館所蔵の「古代製茶図」は茶園管理、摘み取り、製造、仕上げ、保管までが描かれ、江戸時代の製茶を伺い知ることが出来るが、基本、碾茶は蒸した茶を、焙炉(ほいろ)で乾燥するということである。焙炉とは茶葉を炭等の弱火で下から加熱し乾燥させる道具の事を言い、「助炭」と言う和紙を厚く張った木枠や籠を用い、この「助炭」の上で蒸した茶を手作業で乾燥させ碾茶を完成させた。蒸して乾燥した製品が出来上がるまでの時間は3時間以上と言われてきたが、その手あぶり製法は大正時代まで続くことになる。「京都府茶業百年史」から過酷な焙炉を備えた部屋での作業を知ることが出来る。
「蒸した茶葉を揉まずに乾燥する碾茶は高温多湿に耐える構造をもった焙炉部屋で乾燥される。概して土塗の壁面であり、その壁土は厚く塗られ、小窓から少し光線を採るのみで出入り口も閉鎖し、室温は常に摂氏四十五度以上を保つようにする」
蒸された新芽は助炭の上にひろげ「さらえ」と称する竹製の熊手状の道具をもって、撹拌し乾燥を促進し碾茶に仕上げた。この作業を行うのが「焙炉師」と言われる季節労務者であり、酒造りの「杜氏」に通じる所がある。筆者宅も幼いころ大和・天理から「焙炉師」が来られ、5月から6月初めまで寝食ともに生活していた事が思い出される。