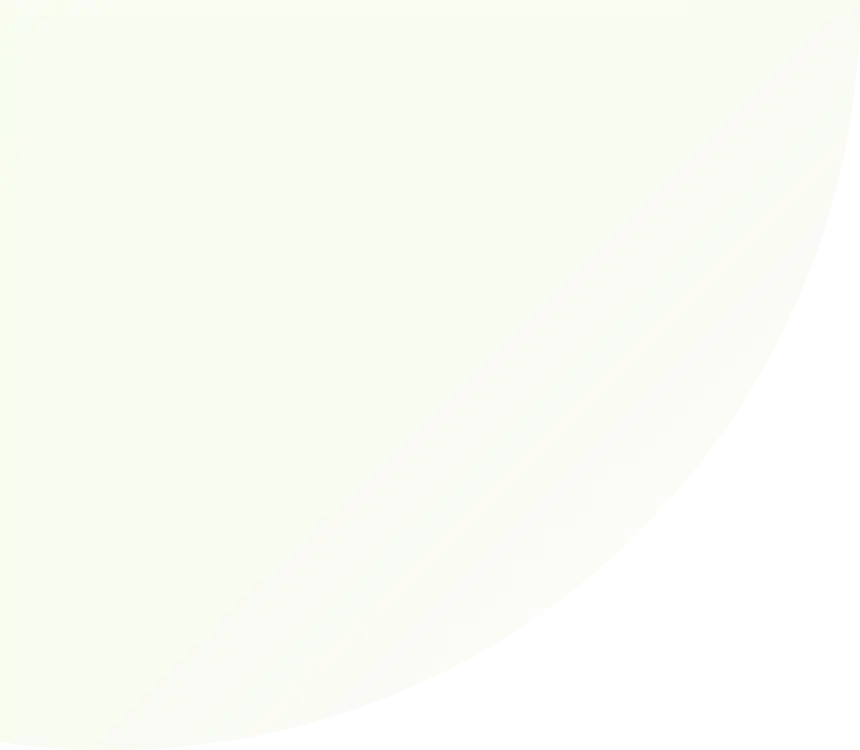

1.栄西と宇治―製茶法をめぐって―

橋本 素子

明庵(みょうあん)栄西(ようさい)は、これまで臨済宗の開祖にして茶祖であるとされ、茶は日本に伝えられて以来禅と共に展開するとされてきました。しかし最近の研究により、顕密(けんみつ)僧として乱れきった仏教界を禅で立て直そうとした「改革派のリーダー」であるという評価に変わっております。
これを受けて拙稿では、宋代の喫茶文化は、日本に持ち帰られて以来、禅宗寺院で広まるのではなく、まずは顕密寺院(※)で広まったことを明らかにしました。それは、南北朝時代成立『異制庭訓往来』の「三月状」に見える茶の名産地の拠点のほとんどが、顕密寺院であることからも裏付けられます。なお第一位は栂尾高山寺で、宇治も第二位グループ6箇所のひとつとして登場しています。
また栄西については、「抹茶」に湯を注いで飲む「点茶法(てんちゃほう)」を紹介したことに注目が行きがちです。しかしその著書『喫茶養生記』には、宋朝に茶を焙(あぶ)る様を見るに、則ち朝(あした)に摘み即ち蒸し、即ちこれを焙る。懈倦(けかん)怠慢の者はなすべからざる事なり。焙る棚には紙を敷く。紙のこげざるように火を誘い、工夫してこれを焙る。緩めず怠らず。竟夜(けいや)眠らず。夜の内に焙り畢(おわ)るべきなり。とあり、栄西が宋で実際に見た、摘採、蒸しによる殺青(さっせい)(熱を加え酸化発酵を止める)、焙炉(ほいろ)による乾燥までの製茶工程を簡潔に記しています。これは、現在の碾茶(てんちゃ)(抹茶の原料)の製造工程と比較すると、栽培方法が「露地栽培」であることを除けば同じといえます。なお、中世において茶臼で挽(ひ)くことは、消費者側が行うものでした。
宇治では、遅くとも鎌倉末期までに、この栄西が紹介した露地栽培の「抹茶」の製茶法を受容したものと考えられます。そしてこれをベースとして、戦国時代末期には宇治オリジナルの「覆下(おおいした)栽培」による「抹茶」を発明することに成功するのです。つまり宇治にとっての栄西とは、覆下栽培の「抹茶」の前提となる、露地栽培の「抹茶」の製茶法を日本に紹介した人物であり、栄西の功績なくしては覆下栽培の「抹茶」も誕生しなかったということになります。
※顕密寺院(けんみつじいん):顕教と密教が勉強できる寺院のことで、密教を基調にする八宗(三論・成実・法相・倶舎・華厳・律の南都六宗と天台・真言の平安二宗)に属する。こちらが中世仏教界の正統である。