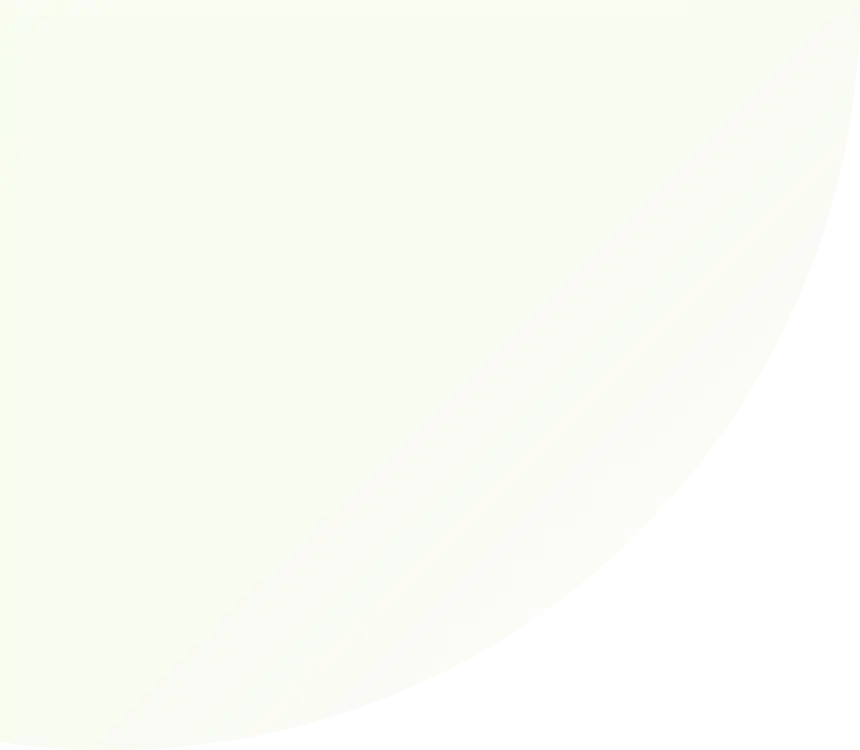

春のにおい

小山 茂樹

さて、「糞」という字を見つめると、つい笑ってしまいませんか。食べたご飯はおなかの中で消化され、やがて米が異なったものになって排泄される。漢字は本当によくできていると思います。この人間の排泄物は農業にとって大切な肥料であり、戦後もだいぶ経ってなお、昭和30年代後半まで各地で有効利用されていました。古く宇治で茶業が発展した理由は、栽培に適した気候風土に恵まれたこと、宇治が茶道の本拠地であり大消費地である京の都に近かったことが挙げられます。しかし、もうひとつの大きな理由は人糞が豊富に入手できたことです。
京都駅から近鉄電車で約15分。宇治川に架かる観月橋を渡ると、右側に巨椋池干拓田が広がっています。ここはその名の由来である「巨椋池(おぐらいけ)」という大池があったところです。都を出発した肥船は鴨川を下り、やがて伏水(ふしみ)を過ぎると宇治川が流れ込んでいた巨椋池に到ります。この大池を利用すれば宇治のどの岸辺へも肥船を着けることができました。『宇治市史』には、頻繁に行われていた江戸時代の人糞取引の記録があって、おもしろいことに上京のものが一番の高値で取引され、御所周辺の人はいい物を食べているから糞もいいだろうと、その理由は実にいい加減だったようです。
人糞は究極の有機栽培ですが、もう使われることはありません。現在の有機肥料として、菜種油粕などの植物性のものと魚粕などの動物性のものとがあり、これらを茶園に施肥しています。有機質肥料は土壌中の微生物によって分解され、やがて土地を肥やし茶樹に吸収されます。速効性の化学肥料に比べて遅効性で、これが「茶づくりは土づくりから」といわれる所以です。間もなく宇治では、「芽出し肥」とよばれる春の施肥が始まります。