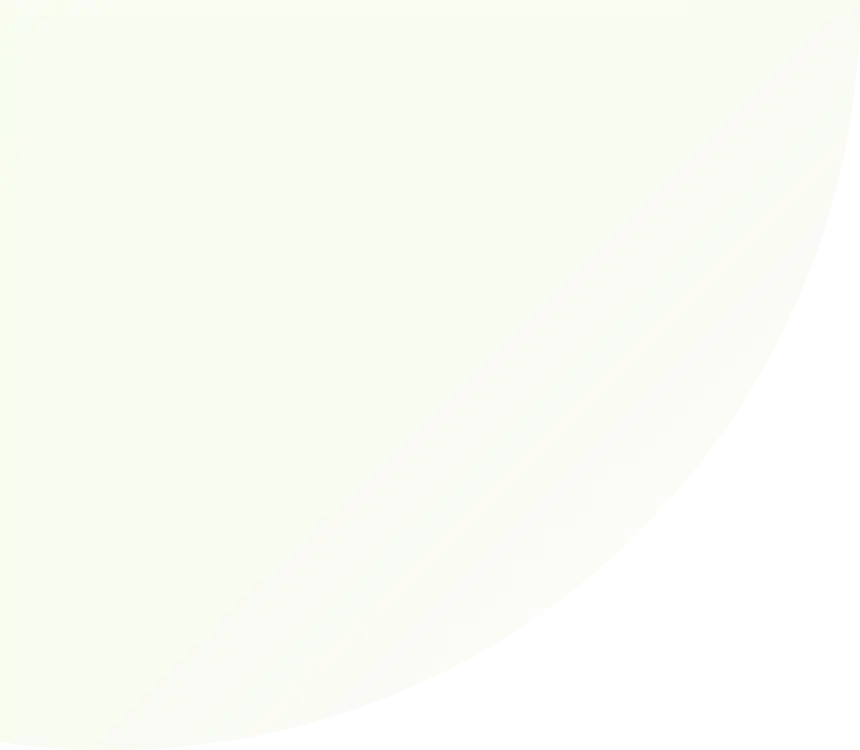

宇治茶はどのようにして作られたのか

林屋 和男

日本に数ある茶の中で、「宇治茶」は日本一強いブランドです。この強いブランドがどのようにして作られたかについて、少し書いてみます。
歴史的には鎌倉時代の始めに、当時宋の国であった中国から茶種を持ち帰った栄西禅師から種を分けてもらった明恵上人が宇治の黄檗の地に茶を植えさせたのが始まりとされています。黄檗山萬福寺の門前にはこれを記念する石碑があるのはご存じの方もあるでしょう。もっとも、それ以前の平安時代にすでに茶が植えられていたとも考えられています。
鎌倉時代には明恵上人の寺のあった栂の尾地区の茶が第一とされていましたが、室町時代には早くも宇治の茶が日本一といわれるようになりました。
なぜでしょうか?
それにはいくつかの原因が考えられます。一つ目は自然環境です。宇治の土が茶の栽培に適していました。また宇治川の川霧は良い茶を育てるのに役立ちます。昼と夜の気温の差が大きいこともあります。これらは、いずれも良い日本茶の条件です。
二つ目は茶を育てる農家の工夫です。少しでも良い茶を作ろうと茶の芽の伸びる時期に覆いを掛けて、日光を遮ることを始めました。これは植物を育てる上ではとんでもないことですが、この逆転の発想がそれまでの苦い抹茶から旨味の強い抹茶を産み出しました。最初は霜除けから考えられたともいわれますが、少しでも消費者に気に入られる品物を作ろうという日本人の気質が産み出したのではないでしょうか。中国から伝わった抹茶ですが、その後中国では廃れてしまいました。苦すぎたためでしょう。茶は元々薬として扱われていましたから、苦くてもしょうがないと考える人と、茶を飲み物として少しでも旨く飲みたいと思う人の違いでしょうか。
三つ目は宇治が都の近くにあって、良い飲み手に恵まれていたことがあります。当時の上流階級の要求によって当時の茶師といわれる茶商はより良い品質の茶を納める必要がありました。
このように自然に恵まれただけでなく、人々の工夫によって「宇治茶」が現在の地位を得ていると思います。今でも宇治茶に携わっている人達は先人を見習い、負けぬよう工夫を重ねていることが「宇治茶」の名声を保っている要因でしょう。
字数が尽きました。次回は先人の工夫について触れてみたいと思います。