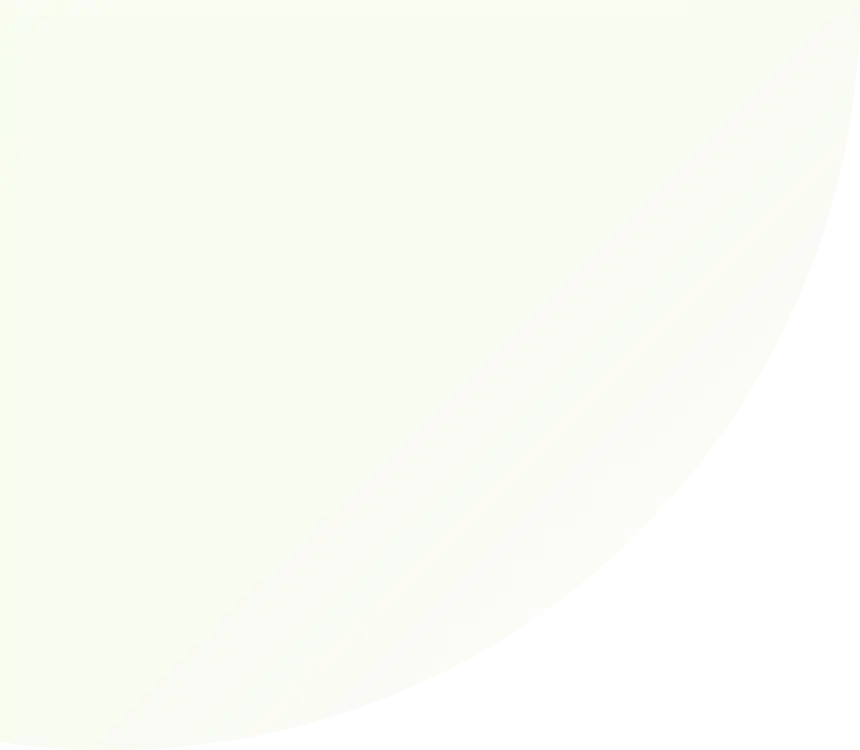


『茶葉を蒸熱、揉捻、乾燥して製造したもの』<生産者が製茶して、仕上加工していない状態の煎茶です。現在では煎茶の製造も多様化してきて、蒸熱の時間が長い状態で作られた煎茶を深蒸し煎茶と言います。また、摘採前の被覆期間(7日程度)がかぶせ茶より少なく、短期間の被覆をして作られる煎茶もあります。>

『荒茶の仕上げ工程で木茎分離機などで選別された茶の茎や葉柄を多く含む茶をいう』<茎茶は、名称が他にもあり、折(オレ)、白折(シラオレ)、棒(ボウ)、骨(ホネ)、雁ヶ音(カリガネ)※が、よく使用されています。> ※雁ヶ音は玉露の茎茶のことを表す店舗もあります。
烏龍茶(ウーロンチャ)は、茶葉を途中まで発酵させてから炒って発酵を止めたお茶(半発酵茶)、中国や台湾が主な産地です。
紅茶(コウチャ)は、摘み取った茶葉を完全に発酵させたお茶(発酵茶)赤みがかかったオレンジ色で、香り高い風味が特徴です。