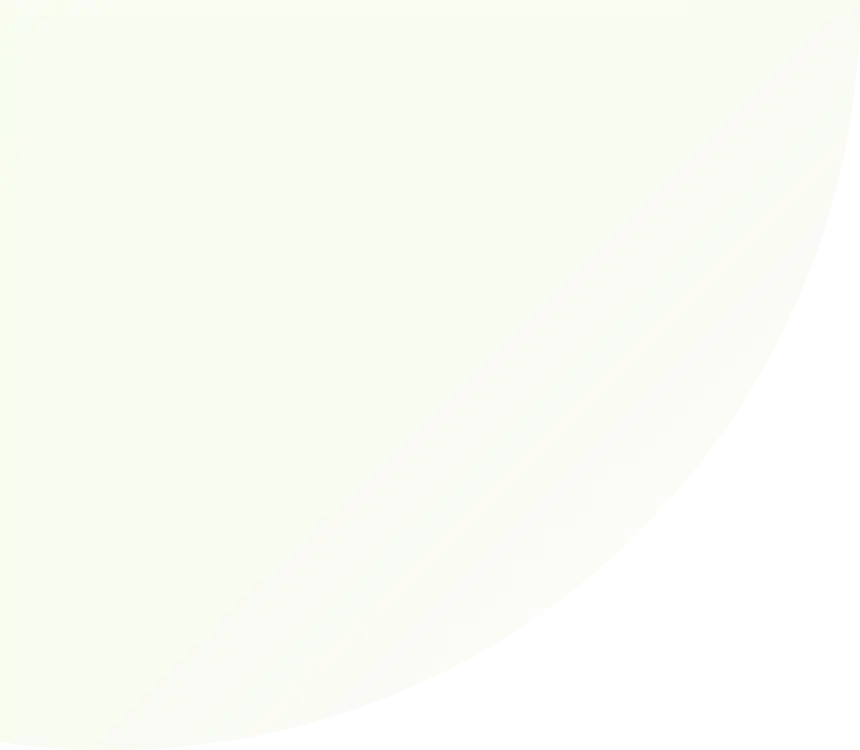
お茶は、米や野菜と同じようにたくさんの品種があり、品種が作られる理由があります。
病害虫に強い茶にして、高品質や多収穫にする。
茶つみ時期が重ならないように早生品種、中生品種、晩生品種を作ることで茶生産をスムーズにする。
売れ筋の茶に仕上がるような特徴のある品種にする。(旨味成分が多い、茶の色が良いなど)
宇治茶は、覆い下の茶の特徴が出るような品種づくりがされています。
種から育てる方法です。種は、画像のように1個、2個、3個というように実の付け方が異なります。3個の実の付け方から「∴」の印が茶畑の地図記号になったようです。
国土地理院HP参照

現在では、実生ではなく挿し木で茶の木は、増やされます。枝を切って苗木にして植える方法です。大きく育った茶の木から、元気な枝を切り取り、土に植えて根っこを出させて苗木にします。1年から2年成長した苗木は、茶畑に植えられます。
「なぜ、種からではなく、挿し木からなの?」
種から育った木は、色んな特徴がでて、栽培管理に手間がかかり、高い品質づくりの妨げになります。例えば、成長の速度が異なったり、病気や害虫の抵抗力が異なったりするので、同じ品種を挿し木で増やすことで、同じ性質の茶の木になり、栽培管理や品質が改善されます。


| 旧系統名 | 平野11号(宇治在来種選抜) |
|---|---|
| 育成年 | 昭和29年 |
| 育成者 | 平野(ひらの)甚之丞(じんのじょう)氏 |
| 摘採期 | 中生(‘やぶきた’とほぼ同等) |
| 樹姿 | 直立型で初期生育が良い |
| 新芽 | 鮮緑色で、葉が薄く大きい |
| 収量 | 中 |
| 品質 | てん茶として特に優秀、出品茶用として多用される |

| 旧系統名 | 小山69号(宇治在来種選抜) |
|---|---|
| 育成年 | 昭和29年 |
| 育成者 | 小山(こやま)政次郎(まさじろう)氏 |
| 摘採期 | 中生であるが適期幅が大きい |
| 樹姿 | 極直立型で手摘みしやすい |
| 新芽 | 淡緑で光沢に富み、みずみずしい |
| 収量 | やや多 |
| 品質 | てん茶として優秀、色沢に冴えがあり、香味に優れる |

| 旧系統名 | 京研170号 |
|---|---|
| 育成年 | 昭和29年 |
| 育成者 | 京都府茶業研究所 |
| 摘採期 | 中生(‘やぶきた’と同程度ないし2日遅い) |
| 樹姿 | やや直立で樹勢は中、株張りはやや大 |
| 新芽 | やや小で葉が薄く、やや淡緑色、光沢やや小で、繊細な形状 |
| 収量 | 中 |
| 品質 | てん茶として、形状はよく揃い柔らかく、色沢は明るく冴え、染まりがよい。玉露として、細くよれて締まりが良く、冴えがある。 |

| 旧系統名 | 「53-38」(さみどり自然交雑実生) |
|---|---|
| 育成年 | 平成18年(昭和52年から選抜を開始) |
| 育成者 | 京都府茶業研究所 |
| 摘採期 | 中生(‘さみどり’と同様‘やぶきた’より1から2日程度遅い) |
| 樹姿 | 樹姿は直立型、樹勢および株張りは中 |
| 新芽 | 新葉は楕円、やや大、やや薄、緑色、光沢と葉質の軟らかさは‘さみどり’と同等 |
| 収量 | ‘さみどり’と同等に多収で、芽重型の収量構成 |
| 品質 | ‘さみどり’、‘あさひ’とほぼ同等で優れる。特に外観では染まりが良く、内質もてん茶として良好な覆い香味が付きやすい |

| 旧系統名 | 京研166号(宇治在来種選抜) |
|---|---|
| 育成年 | 昭和29年 |
| 育成者 | 京都府茶業研究所 |
| 摘採期 | 中晩生(‘やぶきた’より3日遅い) |
| 樹姿 | 中間型で、株張りの広がりが早い |
| 新芽 | 淡緑で葉はしわが少ない |
| 収量 | ‘やぶきた’と同等で多い |
| 品質 | 揮発性の特徴ある香気をもち優秀、玉露の出品茶用として多用される |

| 旧系統名 | 京研307号(宇治在来種選抜) |
|---|---|
| 育成年 | 昭和58年 |
| 育成者 | 京都府茶業研究所 |
| 摘採期 | 中早生(‘やぶきた’より2日早い) |
| 樹姿 | 中間型で初期生育が旺盛 |
| 新芽 | 緑色で大きさは中 |
| 収量 | ‘やぶきた’と同等で多い |
| 品質 | 玉露として色沢、内質ともに優れる |

| 旧系統名 | 「53-7」(さみどり自然交雑実生) |
|---|---|
| 育成年 | 平成18年(昭和52年から選抜を開始) |
| 育成者 | 京都府茶業研究所 |
| 摘採期 | 極早生(‘さみどり’に比べ7日程度早い) |
| 樹姿 | やや直立型、樹勢及び株張りは中 |
| 新芽 | 新葉は長楕円形、やや大、緑色、光沢やや少、やや軟 |
| 収量 | ‘さみどり’と同等に多収で、芽数型の収量構成 |
| 品質 | ‘さみどり’とほぼ同等で優れ、内質は香気が強く、新鮮みがあり香味に優れる |
京都府茶奨励品種の栽培特性一覧PDF
協力:京都府茶業研究所