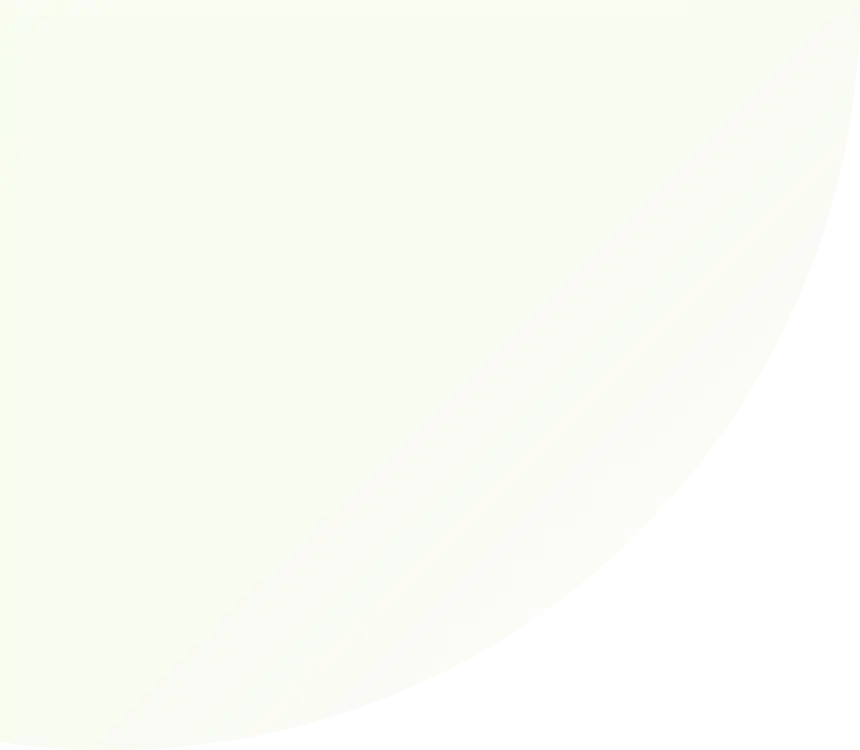
元文3年(1738年)綴喜郡宇治田原町湯屋谷の人 永谷宗七郎翁(宗円)が、青製煎茶製法を創案した。それまでは、中国の流れを汲み、茶の芽を釜でいって、ムシロの上で手足によって揉み、日光で乾燥させた釜いり茶といわれるものであった。翁は、この製法を改良し、茶の芽を蒸した後、ホイロで乾燥しながら手でもむ製茶法(青製煎茶製法)を始めた。
この茶は、従来の茶に比べて色沢香気ともに優良で、江戸を初め各地において好評を博した。その後、多くの人々によって改良を加えながら今日の手もみ宇治製法(宇治手もみ製法)が完成された。
この手もみ製法が全国銘茶産地に広められ、現在各地で保存されている手もみ技術の大半は、宇治製法の流れを汲むものと思われる。
吉田喜三郎翁が保持していた玉露の手もみ製法は、この宇治製法を正しく受け継ぎ、更に技術の改良を加えたものである。
昭和44年3月3日宇治茶製法技術保存協会が結成され、翌年宇治市白川にある京都府立茶業研究所内に宇治手もみ工場が建設され、同年10月「宇治茶手もみ製法」が無形文化財に指定、その保持者として吉田喜三郎翁が認定された。
毎年この工場では後継者による手もみ競技会が行われ、吉田翁の指導のもとに手もみ製法の保存に努めていたが、惜しくも翁は、昭和58年7月9日に死亡された。そのため認定は解除された。しかし、その貴重な技は宇治茶製法技術保存協会の会員に伝えられており、昭和61年4月25日にその技術保持団体として宇治茶製法技術保存協会が無形文化財として指定を受け今日に至っている。

・生葉 約3kg
・木炭 約3.8kg
・ワラ 約5.5kg(4~5束)
・少量の灰
を用意します。

生葉を蒸す。
蒸葉約3kgを1焙炉量とし、軽く指先を動かし、助炭面にすり付くことなく茶葉を小手にかき上げ(高さ30cm~40cm)一面に振り落とす。その際、葉と葉が重なり合わないように敏速にかつ平均に行うこと。その度合いとしては、投入茶量の3割程度とする。
(なお、操作の際、茶を助炭につけないようにすること。)
最初は、助炭全面を利用し、軽く転がす。乾燥するに応じ漸次力を加え、最後約20分程度は充分に力を入れる。
横まくりの際、出来た塊を解くもので、最後の横まくりが終われば次第に力を弱め、手早く回転して大塊を解きほぐす。
玉解き後、一旦助炭から取り出し、揉み茶の水分を均一にし、かつ冷却を行う。なお、この間に助炭面の掃除を行い、次の操作に対する準備を行う。
この際における水分減は投入量の5割減。
(冷却中の茶についても、揉み切り等により小塊にいたるまで充分に解きます。)
片手まくり及びもみきりを交互に行うが、片手まくりは充分に力を入れて一工程7回以上行うこと。
(この際、葉揃えにも充分注意すること。)
葉のむれ及び上乾きを防ぎながら、より形を整えつつ製茶の香味をよくするために行う。茶を軽く持ち上げるような感じで、手を左右に交互にもむ。最初軽く、乾燥するに応じて力を入れ、茶を助炭中に広げぬようにし、茶に丸みをつける心持ちにもむ。
(この際、あまり力を入れすぎると助炭が破れる。)
形状を丸く伸ばし、色沢、香気をよくするための最終操作で一旦茶を片隅に寄せ、残った粉を助炭に糊付けし、揉み茶のすべりを少なくすると同時に、別に板ずり用の板をはめる。茶を板につけて両手にて葉揃えをしながら上下に旋転摩擦する方法で、最初は丸みをもたす感じで茶全体が返る様、握った茶は逃がさぬ様。この時、力は最後までゆるめぬ様にする。
もみ上げの時期は、形も整い茶に艶がつき、手から茶が滑り始める時とする。
仕上げ終了後(約60℃)の助炭に薄く拡散し、時々反転し乾燥を行う。
所要時間:約4時間(乾燥を除く)