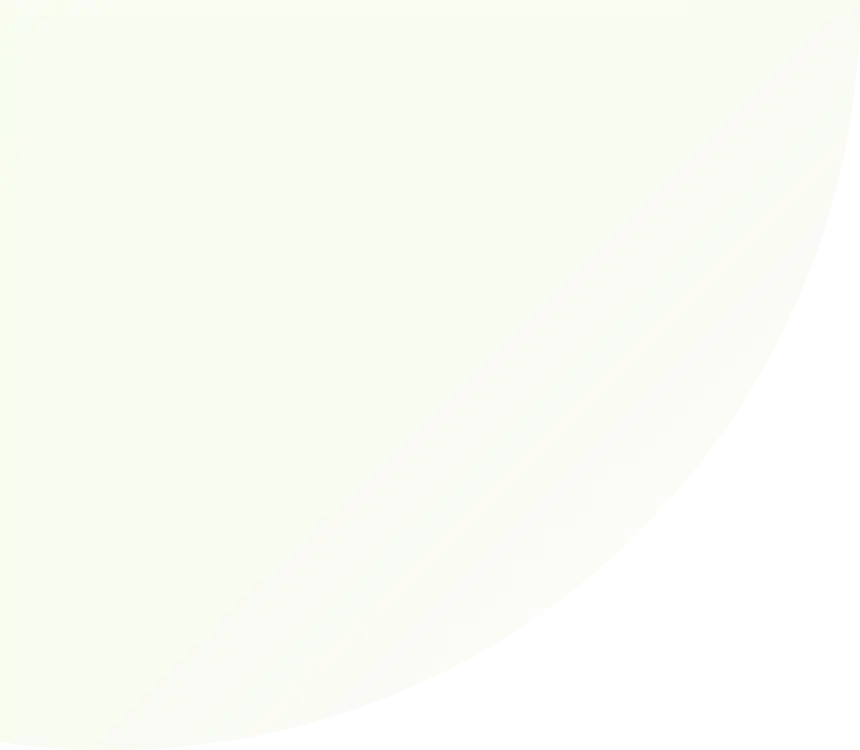
日本のお茶の歴史は鎌倉時代より古く、その始まりは中国から伝わってくるものが多いです。
宇治茶の始まりがどの時代なのかは確実に言えませんが、
様々な研究がされており、現在考えられる説で説明をします。
鎌倉時代の始め、禅宗が中国から伝わりました。その時にお茶の苗木(種)と飲み方を日本に持ち帰ったのが、臨済宗の栄西(ようさい)禅師と言われてます。臨済宗の本山は、建仁寺で京都にあります。明恵上人は、栄西禅師と親交があり、お茶の苗木をわけてもらい、同じ京都にある高山寺に植えました。当時のお茶は、薬としての役割が大きく、京都を中心にお寺を通じて全国に広がっていきました。その広がっていく地域の一つに宇治がありました。
室町時代の始めの南北朝時代には、ある遊びが流行しています。闘茶と言ってお茶を飲んで、そのお茶がどこの地域で作られたお茶であるかを当てて競い合うものです。
その当時、茶寄合という集まりがあり、そこに集まった人たちで闘茶を楽しんだとも言われてます。当時の闘茶の流行ぶりは、賭事にも発展し、風紀を乱すとの事で幕府から禁止令が出ているくらいです。
鎌倉時代から比べると、お寺での薬としてのお茶から、飲んで楽しめるお茶に変わってきたようです。
室町時代の応仁の乱以降には、お茶の飲み方と作り方に変化がでてきます。飲み方は、茶寄合など派手な飲み方から質素で外面より内面を重視した「わび茶」が誕生します。この時代に宇治で品質を上げる技術革新が起こってます。それは現在にも続く覆下栽培の始まりです。この栽培方法によりお茶の品質(旨み成分)が、かなり上がったと考えられます。この技術革新もともなって「わび茶」は更に進化していきます。
わび茶が、戦国大名の間に浸透すると、さらに洗練された茶の湯(茶道の始まり)が、流行り始めます。その第一人者であるのが、千利休と言われています。やがて、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康が天下人の時代は、激動の時代とともに茶の湯と抹茶のクオリティの素晴らしさが、全国に広がっていきます。一つの考え方ですが、長く続く戦乱で疲弊した心を癒すパワーが、茶の湯のお茶の成分(リラクゼーション効果があると言われているテアニン)に、効果があったかは、興味深いところです。
戦さのない泰平の時代に入っても天下人が愛したお茶は、ステータスとして、茶道とともに受け継がれていきます。そのお茶は、宇治で採れる、当時の高級品質であった宇治抹茶であり、茶仲間という、特定業者のみに徳川幕府は、製造を許可することで、将軍家や大名家の御用達となり、宇治で採れたお茶を茶壺に詰め、江戸までの大名行列ならぬ、御茶壷行列により運ばせました。これにより宇治抹茶が、権威のあるブランド商品となった時代ではあると考えられます。
泰平の世が続き、町人文化といわれる元禄文化の時代に煎茶は登場しました。宇治抹茶は、茶仲間の独占販売と将軍大名が取引先であるため、永谷宗円翁は、それまでのお茶の製茶方法を改良し、茶葉を蒸してから段階的に揉みながら乾燥させる方法で煎茶という新たなお茶を作り上げました。煎茶は江戸で販売を始めたところ町人文化の花咲く江戸で、大ヒット商品となり、江戸末期には、狂歌に出てくるほどになりました。
「泰平の眠りを覚ます蒸気船(正喜撰)たった四杯(4そう)で夜も眠れず」当時浦賀にやってきたペリーの黒船4隻が来て開国を迫った歌。蒸気船と正喜撰(当時江戸で高級な煎茶として有名)を掛け合わせ、さらに4隻と4杯を掛け合わせた歌、旨味のあるお茶は、カフェイン含有量も高く、たくさん飲むと眠れなくなるので、正喜撰は旨味のあるお茶だと考えられます。
江戸時代末期になると、幕府や大名家は財政が厳しくなり、高級な宇治抹茶の購入が滞り始めます。さらに宇治では大火事により茶園や道具などが消失したため、茶仲間も経営が厳しくなり、これまで発展を続けてきた抹茶に陰りが見え始めてきます。煎茶が町人たちに広まっていく中、新たな茶種が生まれます。それが玉露です。玉露は、碾茶と同じ覆下栽培であるため、碾茶から玉露への方向転換は、宇治では容易であったと考えられます。そして江戸幕府が終わりをむかえると、宇治の抹茶は、最大の取引先である将軍や大名を失い明治を迎えることになります。
開国しましたが、輸出する産品が乏しく、日本の輸出産業としては、生糸の取引額が、1位という状況でありました。そして二位は、緑茶でした。この緑茶は、主に煎茶であり、江戸(東京)から駿府(静岡)に移動した徳川幕府の御家人、旗本を中心に煎茶の栽培に取り掛かり、下田や清水からアメリカ向けの煎茶が輸出されることで、煎茶の一大産地になっていきます。その時、京都は、和束町や南山城村をはじめとする京都府南部エリアに煎茶の生産地を形成し、特に山城町(木津川市)は、その加工地として、発展しました。さらに木津川の水運を利用し、大阪や神戸からアメリカへ輸出されました。
日本の輸出産業を支えてきた緑茶は、粗悪品が混ざり始め対米輸出がストップするようになります。では、日本の輸出額第二位の量であったお茶は、どこへ行ったかというと、海外から国内に市場が移ることになります。日本人が、急須でお茶を飲むということが、日常茶飯事になる一つのきっかけだったかもしれません。
その頃の宇治抹茶というと、明治以後女子への教育の広がりのなかにおいて、学校教育の一環としての茶道が普及され、茶道により宇治抹茶は一般庶民への広がりを見せます。
昭和に入り、戦争という暗い影は、茶業の中にもやってきます。特に宇治抹茶は贅沢品という位置付けで、規制対象になりやすい中、京都府茶業研究所は、その宇治抹茶の効能を生かした、抹茶を固めて食べやすくした抹茶錠を作り、軍への物資として供給されました。
戦争が終わり、高度経済成長に合わせるように茶業も日本国内で好調に回復してきました。そして平成のバブル期には、高級茶の注文が増えましたが、自動販売機やスーパーマーケットさらにはコンビニの増加により、お茶の流通形態も変化し、街の茶小売店が減少していきます。さらに飲料の多様化にあわせ、日本人の煎茶離れが進み、急須がない家庭が急増します。そのような中、それまで茶道関係が主な取引先でありましたが、抹茶の食品原料としての利用が、増えてきます。生産現場では、玉露や煎茶の生産者が、碾茶生産に次々にシフトするのが平成の時代でした。令和になってコロナ禍による消費の落ち込みは、茶業にも降りかかり、大ダメージを受けました。しかしコロナ禍明けにインバウンドの増加により、空前の抹茶ブームが来ました。このため、京都の茶市場での取引額が開設以来の売上高を記録しました。
宇治茶は宇治抹茶が発展し、宇治煎茶が誕生し、それが全国に広まり、さらに玉露が誕生することで、日本茶の代表3茶種が揃います。どの茶種も時代の流れにより、好不調が今までもあり、この先もどのような流れに変化するか予測不能です。
ただし、宇治茶の先人たちが繋いできた顧客への満足を高める創意工夫は今も受け継がれていて、「伝統」と「変革」を重ね未来に宇治茶の素晴らしさをつないでいきます。
参考資料
「日本の茶 歴史と文化」吉村亨・若村英弌(淡交社)
「日本茶の歴史」橋本素子(淡交社)
「抹茶の研究」桑原秀樹(農文協プロダクション)
「茶壺に追われて」小山茂樹(淡交社)
「京都府茶業百年史」京都府茶業会議所